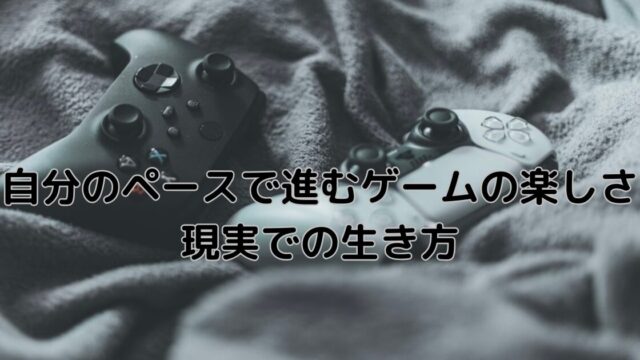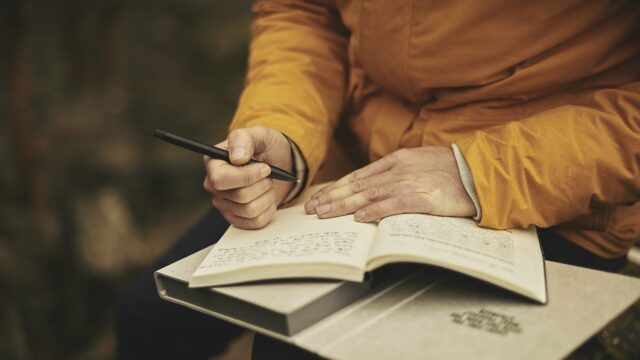先日、Twitterでこんな投稿を見かけました。
「子供に強めに注意してしまった。怒ったつもりはなかったけれど、あとから反省している」という内容です。
読んだとき、僕は障害者介護の現場での自分の経験を思い出しました。
感情的になったわけではないけれど、「ちゃんとしてほしい」「危ないことは避けてほしい」と思うあまり、つい強い口調になってしまったことがありました。
でも相手の反応を見ると、「怒られた」と感じてしまったのかもしれないと気づき、言葉がうまく届いていないことに後から気づくこともありました。
基本的に僕は怒るタイプではありません。
だけど、人に迷惑をかけたり、筋が通っていないことに対しては注意をします。
自分がそれを好きではないからだけでなく「しっかりしてほしい」という気持ちがあるからです。
とはいえ、自分がどんなに冷静に伝えようとしても、相手から「怒られた」と感じられてしまうことがあります。
声を荒げたわけでもなく、言葉遣いにも気をつけていたつもりなのに、伝わる側の感じ方や背景によって、受け取り方は大きく変わるのだと痛感しました。
「叱る」という行為は、ただ正しさを伝えればいいわけではありません。
どんなに内容が正しくても、受け取る側の心が閉じてしまえば伝わらないのです。
自分の「正しさ」は時に相手を追い詰めてしまう刃にもなりうる。
だからこそ、「怒る」と「叱る」は根本的に違うものだと思います。
では、どうすれば伝わる叱り方ができるのか。
僕なりの答えは、「相手の背景や気持ちを想像すること」です。
例えばルール違反をした方に注意するときも、「なぜそうしたのか」「どんな事情があるのか」と想像するだけで、言葉のトーンや伝え方が変わってきます。
言いたいことを伝える前に、相手の立場に立ってみる『間』を持つ。
それだけで、ただ「怒られる」のではなく「伝えられている」という受け止め方に変わることがあります。
叱ることは、本当はすごく丁寧な行為です。
その人の可能性を信じて、目をそらさず伝えること。
でも同時に、相手の状況や気持ちを受け止める「余白」も必要なのです。
それでも、伝わらないこともあります。
社会的に正しいことを言っても、価値観や背景が違えば、相手には押しつけに感じられてしまうこともあるでしょう。
どんなに言葉を選んでも、相手が「怒られた」と感じてしまえば、それがすべてです。
だから、「叱る」というのはとても繊細なバランスの上に成り立っています。
正しさだけでは届かない。優しさだけでも伝わらない。
その間を行き来しながら、相手に届く言葉を探し続けることだと、最近ようやく気づきました。
私は今でも、「怒る」と「叱る」の違いを自分に問い続けています。
うまくできなかったときの後悔も覚えておく。
大切な人にしか『叱る』ことはしません。
そして、また誰かに何かを伝えたいと思うとき、少しでも伝わるように努力したいと思います。
伝えることは難しい。
でも、その難しさを知っているからこそ、真剣に向き合いたい。
相手との距離が縮まるかはわからないけれど、少なくとも「この人に伝えたい」と思った自分の気持ちは大切にしたいのです。